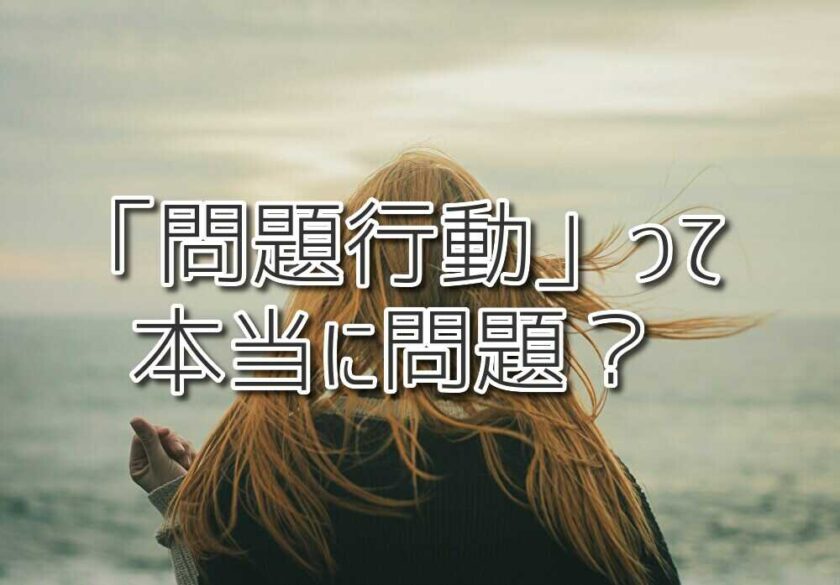【ASTEP LABO】開所をしました!
正直なところ、まだまだ手探り状態です。
毎日、お子さんたち一人ひとりの特性をつかみながら、安全に気をつけて、支援の方法を考えては修正して…その繰り返しの日々です。
でも、まだ1ヶ月も経っていないのに、それぞれのお子さんたちに、小さな成長の芽が見え始めてきてるんですよね。
もう、嬉しくてたまりません…!
親御さんとのコミュニケーションも、まだまだ活発ではないものの、これから少しずつ距離を縮めていければと考えています。
さて、LABOでの療育を開始して感じたことを、またつらつらといつものように言語化していきます。
LABOの子どもたちは、一人ひとりめちゃくちゃパンチがあって(良い意味ですよ!)色んな特徴やカラーがあるということ。
お会いする相談員さんには「噛み応えのある子たちです(これも良い意味ですよ!)」と伝えるほど、粒ぞろいの個性派たちです。
その中で、私たち支援者から見ると「どうしてこんな行動をするんだろう?」と思うような場面が毎日のようにあって、新しい発見の連続
今日は、そんな子どもたちの行動について、特に「問題行動」と呼ばれるものについて、少し掘り下げて考えてみたいと思います。
問題行動ってほんとうに問題?
「問題行動」という言葉、聞いたことありますか?
自閉症や行動に特徴のある人たちが、パニックを起こしているような状態だったり、まわりの人が「それは困るなあ」と感じるような行動をしているときに、よく使われる言葉。
たとえば、支援者の声かけに応じずに自分のやり方で動いてしまったり、ルールを無視して、自分だけのルールで行動しているときとかですね。
いろんなパターンがあるんですけど、共通して言えるのは、この「問題行動」という判断をしているのは、支援者側だということなんです。
つまり、「本人が問題だ」と決めているわけじゃなくて、支援する側の私たちが「これは問題だ」と見なしているってことなんですよね。
じゃあ、そもそもこの「問題行動」っていう言葉、どうして生まれたの?と気になって考えてみたんですけど…
ちょっと頭をぐるぐる、想像してみると…
支援方法をまだうまく身につけられていない支援者が、相手の行動がよくわからなかったり、コミュニケーションが取れなかったりして、困り果てたときに生まれたんじゃないかなと思うんです。
「自分は一生懸命やってるのに、うまくいかない」「それは相手が悪いからだ」っていうふうに、自責で支援者自身の力不足を見直すんじゃなくて、他責で相手に責任を押し付けるために作られた言葉なんじゃないかって。
「自分たちは一生懸命やってる。それに応えない彼らが問題だ。私たちは悪くない。」
そんな構図なのかなぁと…
でも、その「問題行動」って、本当に問題なんでしょうか?
その行動が起きたとき、あなたはその前にどんな関わり方をしていましたか?
あなた自身、その子への支援に「難しさ」を感じていませんか?
あなたの事業所は、その人に対して、きめ細やかな支援をしてる?
いろんな問いを立てて重ねていくと、見えてくることがあります。
もしかしたらその子は、自分の困っていることを、あなたが「適切」と思う方法では伝えられなくて、独自のやり方で表現しているだけかもしれません。
そして、あなた自身がどう支援したらいいかわからないから、その人を「問題扱い」してしまっている可能性、ないですか?
だとしたら、本当に「問題」なのは、障がいのある子どもの行動ではなくて、その子に合った支援方法を持っていない、私たち支援者側なんですよ。
でも、「一生懸命やってるから」と、自分たちの問題にはなかなか目を向けられない。
そんな論理になってしまっている可能性、ありますよね。
もし、支援の方法を変えて、それが上手くハマれば、、パニックも問題行動とされることも、そもそも起きないかもしれないんです。
彼らが行動するときには、ちゃんと「必要な情報」があって、その伝え方も一人ひとり違います。
情報を受け取ったり、処理したりするところに障がいがあるからこそ、どう行動していいかわからなくなったり、その時の気持ちを独特な形で表現することもあるわけです。
だから、もし「問題行動」を起こしてしまっているとしたら、支援者である私たちが、もっとわかりやすい支援を届ける努力をしないといけないんです。
問題行動は、なくすことができます。それには支援が、先に必要なんです。
いつまでも、「この子に問題がある」と言い続ける支援者は、その視点を持つだけで思考や行動を変えられるかもしれませんよ◎
それぞれの「支援者としての質」が問われています。
問題は相手にはない、私たちの中にある。
さらに言えば、「困った行動」じゃない。子ども自身が「困っている行動」なんです。
だからこそ、学びたい!
特に、行動が表面化している子どもから、たくさんのことを教えてもらいましょう。
「あなたと話したい。私の困りごとに気づいてほしい。」
そんな、声なき声を、私たちが聴こうとすることから、すべてが始まるんじゃないでしょうか。
お問い合わせはこちら