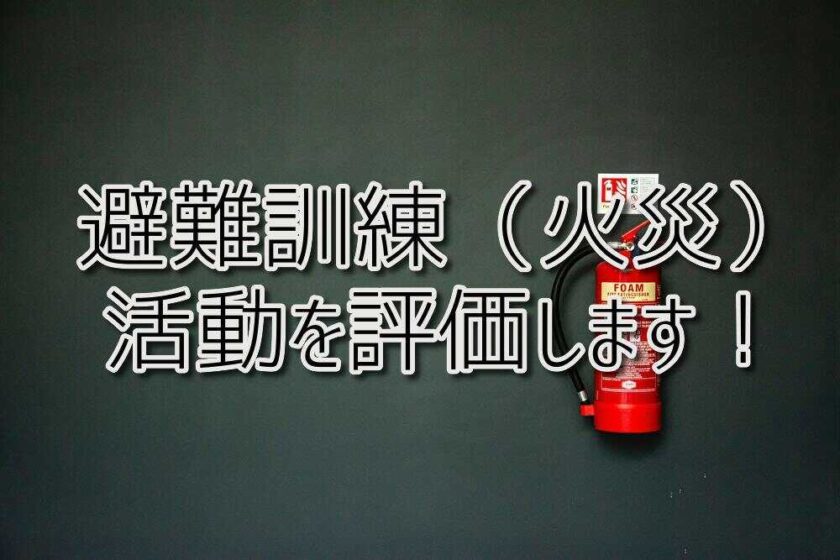こんにちは!こんばんわ!
まずは告知でさせてください★
先日、新規事業所『ASTEP長岡京』物件契約が無事完了しました。
内装などの工事は今からになりますが…ご利用を検討されている方、どしどしお問い合わせいただき見学にお越しください!
〖News〗でどんどん情報発信していきますので是非チェックを宜しくお願いします!
今回の評価ブログは、先日行った避難訓練、想定は『火災』です!
ASTEPのような放課後等デイサービス施設は、建物が特定防火対象物と指定されているため、年2回以上の消防訓練が義務づけられています。
今回は火災時を想定して訓練を行いましたが、その他にも、台風・地震・津波・噴火など、法令で求められている消防訓練の範囲は広く求められています。
実施した訓練では、向日消防署さんにご協力をいただき訓練を行いました。
以下、訓練の内容と評価になりますので是非ご覧ください★
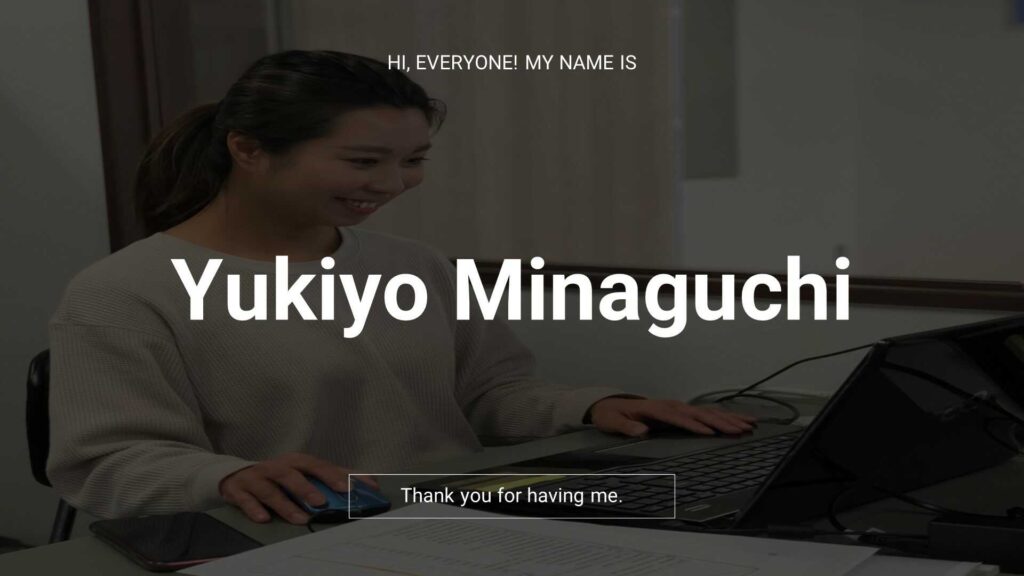
立命館大学・政策科学部卒~某アパレル企業に就職~結婚を機に退職
父が特別支援学校の校長だったこともあり、児童福祉の道へ進むことを決意!
現在は、2021年にASTEPを立ち上げ、仕事と子育て(2児の母)の両立を目指し日々奮闘しています!
目次
訓練の目的
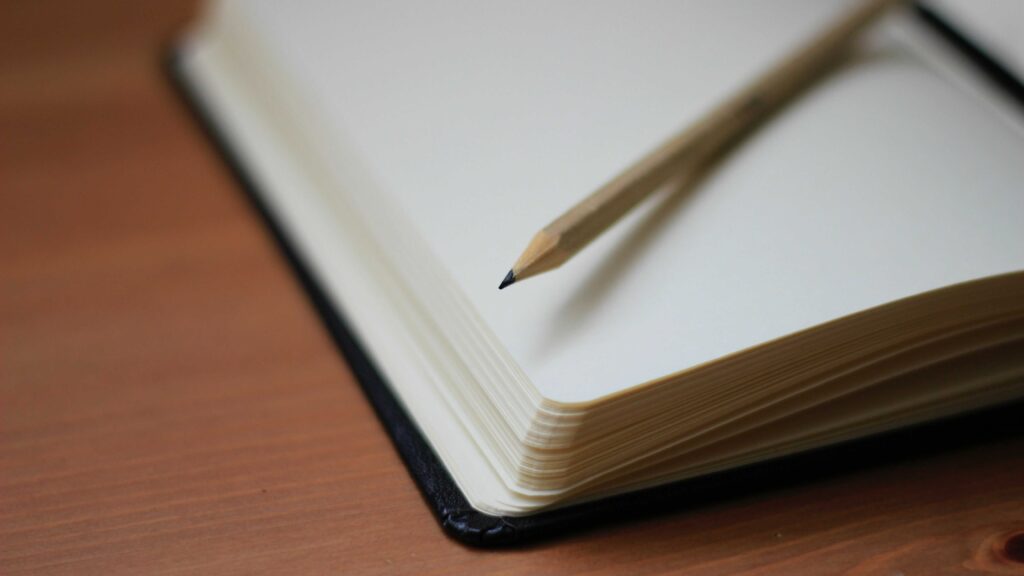
- 防災への意識付けと火災発生時における事故防止
- 安全に避難する方法や順序を概ね体得する
- 指導員に対し、緊急時体制の確立を周知徹底し、防災意識の向上に努める
- 事業所内での連絡及び協力体制を強化し、他の関係機関との連携を図る
大きくはこの4つです!
子どもたちが防災意識を持って日々生活をするということは現実的ではないため、今回はシンプルに『防災』ってこういうことなんだよ!というような形でイラストをもってインプットをしていきました。
火災の際に亡くなる一番のリスクは火ではなく煙であると言われています。
自分の身を守るための避難の方法、おはしもて(押さない・走らない・しゃべらない・戻らない・低学年優先)を確認し、実際に行動に移すところまで行いました。
また、子どもさんのためだけの避難訓練というわけでなく、子どもたちの命を守るのは指導員ですので、緊急時を想定して、指導員に対しては緊張感を持って訓練に臨むよう要求しています。
子どもたちの命が危険にさらされている緊急時に必要なことは、各指導員の役割をはっきりとさせること。
ASTEPでは…
| 施設管理者 | 利用者に被害の有無、事業所及びその周辺の被害状況の確認(事業所携帯①持ち出し) |
|---|---|
| 指導員A | 訓練通報を実施、利用者の人数を確認、利用者の先頭に立ち避難誘導を開始(事業所携帯②、救急バッグの持ち出し) |
| 指導員B | 利用者の最後尾に位置し、残っている利用者がいないか確認、遅れのないよう速やかに避難誘導する。(事業所携帯③、利用者名簿の持ち出し) |
| 指導員C | 避難誘導列の中間に位置し、利用者の安全を確保しながら避難誘導する。その際、可能な限りの重要物の持ち出しと事業所の施錠を実施 |
定員10名の場合、安全に避難をするためには、最低でも4名の人員が必要となります。
ASTEPでは常時5~6名を配置しているので、余剰の指導員は『指導員B』に配置をしています。
また、連絡体制を確立する観点から、管理者と指導員A・Bに事業所携帯の持ち出しをマニュアル化しています。
今回の訓練でも、離れた場所にいる施設管理者(私)が各指導員に連絡を取り、状況の把握を行いました。
このように、避難訓練は単純に行うものではなく、大人と子どもが協力して命を守るために何をしなければいけないのか?を考えて実践する良い機会なのです。
その他、子どもさんの中には、パニックになったり突如具合が悪くなり動けなくなる子が出てくることも想定されるので、そういった場面で誰が責任を持って避難をさせるのかを、予令なくその場で施設管理者である私が指示を出し、指導員の動きをチェックしていきました。
訓練の流れ

- 16:20に訓練119番通報を実施(乙訓消防本部と調整済み)
- 火災発生時を想定、避難経路を教え確認
(聴覚過敏の利用者に配慮し、火災のベル等は鳴らさない) - 速やかに安全な場所(向日市競輪場)に避難
- 向日消防署へ移動、簡単な講話や訓練用消火器体験、消防車や消防用具の見学・質問
時系列で列記しています。
事前のインプットで煙を吸わないようハンカチなどで鼻と口を覆い、避難する体勢をインプットを行っています。
訓練ということで、聴覚過敏の子どもさんに配慮をして火災報知器の作動は今回は見送っています。
避難後、そのまま向日消防署に移動して、講話を聞き、消防車の乗車体験、消火器の取り扱い体験を行いました。
訓練の様子・評価

今回の訓練の重点項目は以下4つを設定しました。訓練中の様子や評価をしていきます!
- 利用児童は指導員の指示を聞き、安全且つ静かに行動すること
- 避難経路を確認し、安全に避難を行うこと
- 反省会を活用し、利用者の防災意識の高揚に資すること
- 指導員は、利用児童の安全誘導を最優先すること

おはしもて(押さない・走らない・しゃべらない・戻らない・低学年優先)を紹介し、火災時に避難する体勢や行動を展示・指導していきました。
危機的状況の経験がなく、想定をイメージしにくいため、子どもたちには「大好きな人とまた会えるようになるため」ご飯が好きな子どもさんには「大好きなご飯がお腹いっぱい食べられるようになるため」と、イメージしやすい言葉で意識付けをしました。イコールすると〖生きるため〗、良い言葉掛けだったと振り返っています!

訓練通報後、速やかに避難場所の向日町競輪場に移動しました。
指導員の位置(前・中・後)や非常時の持出し物品、携帯電話で子どもさんの所在を確認しました。
屋外での活動では日常的に所在確認のための連絡を行っていることからスムーズに行うことができました!
子どもたちも訓練と分かっていることでやや緊張感がなく、静かに移動ができたかというとそうでない場面もありましたので、この点は課題ですね!
過敏な子どもさんへの配慮とある程度の緊張感を持たせる想定…難しいところですが次回に生かしたいと思います。

避難訓練後、向日消防署に移動しました!
まずは講話から開始しましたが、消防車や救急車見たさに体が動いてしまう子どもさんも…
事前にイスを配置して『これから話を聞くんだ〗と見ただけで意識できる工夫や、落ち着いて講話を聞く配慮が必要だったと反省しています。
事前の打ち合わせで『要点を絞って短めに』という要望を聞いてくださった消防士さんに感謝します★

消防車内の装備を見学しました!
消防士さんのヘルメットをかぶらせてもらったり、酸素マスクを背負わせてもらえるなど貴重な体験をさせてもらいました!
ホースがぐるぐるに巻かれているのを見て「どうやって出すの?」と質問をぶつける子どもさんもいました。
物事に対して疑問を持てることは、思考を深めるために欠かせない作業です。
「消防服は何でテカテカの黄色なんだろうね?」など指導員から子どもたちの疑問を引き出すための言葉掛けを行っていきました!

救急車の中の見学です。
見たことのない機械がたくさん乗っていて興味津々の子どもたち★
その興味や好奇心が日々の生活や活動の根源となります!
パルスオキシメーターをつけられた子どもさんの中にはビリビリと電流が流れると思い込む子もいたり…想像豊かでほのぼのしました!

消火器を持ったことのない子どもさんが多くて意外にびっくり…!「重たー!」と本音が漏れる場面も★
よいしょよいしょと重たい消火器を必死に運ぶ低学年の子どもさんです!順番を決めて消火訓練の開始です!

訓練用の消火器を使って消火体験を行いました!
思っていた以上に噴射する勢いがすごくて、子どもたちも的当てゲームのような感覚で訓練を楽しんでくれました★
いざという場面では大人が消火器を扱うことにはなりますが、学童期にこういった体験をしたことがあるかないかで、大人になった時、いざという場面で動けるか動けないか変わってくると思いますし、何よりやったことがあるという『自信』になりますよね!貴重な体験をありがとうございました!
さいごに
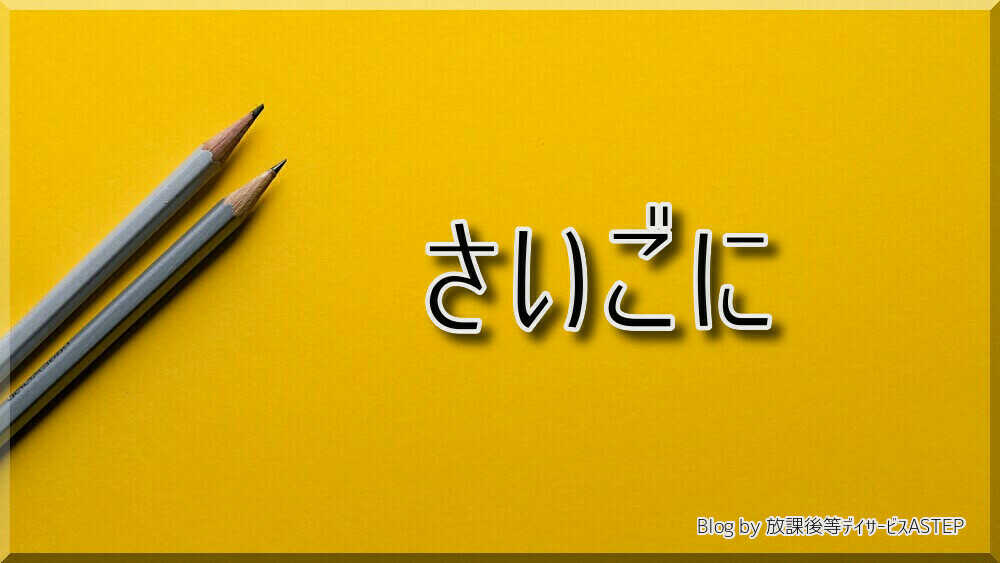
記憶が新鮮なうちに、指導員間で早々に振り返りと反省・記録を行い、ブログに綴らせてもらいました。
『ただ移動するだけ』という形式的なものにならないよう指導員の配置や連携を中心に訓練を行いましたが、まだまだ改善の余地があり今後の訓練プランを見直さなければなりません。
多くの避難訓練は避難するまでが目的となりがち(避難→終了→反省)ですが、避難後の行動や対処についてもしっかりと認識を合わせようという意見も出ました。
- どこに待機するのか?
- どれぐらい待機するのか?
- 子どもの健康状態の把握(チェック表など)
- 通報すべきところ(保護者・管轄行政)
待機場所の目印となるような物の設置や、寒い時期であれば長時間その場に居続けられないなどの状況も考えられます。
ASTEPでは、事業所マニュアルに基準となる項目を明確に策定していますが、子どもさんの特性や時期的な特性も踏まえ、日頃から「もし今事態が起きたら?」という意識を常々持っていないと、いざという時に適切に行動することができないという結論に至り、形式的な訓練ではなく、焦点を絞った訓練を継続して行うことで意見がまとまりました。
必要に応じて事業所マニュアルをこまめに見直すとともに、危険見積りを含めた日頃から防災への意識(特に指導員)を保持するための研修を行っていきたいと考えています。
次の避難訓練の想定は『地震』になります。
今回の反省を踏まえ、次回の訓練でも準備をしっかりと行い、実りある訓練にしていけるよう努めていきます★
お問い合わせはこちら