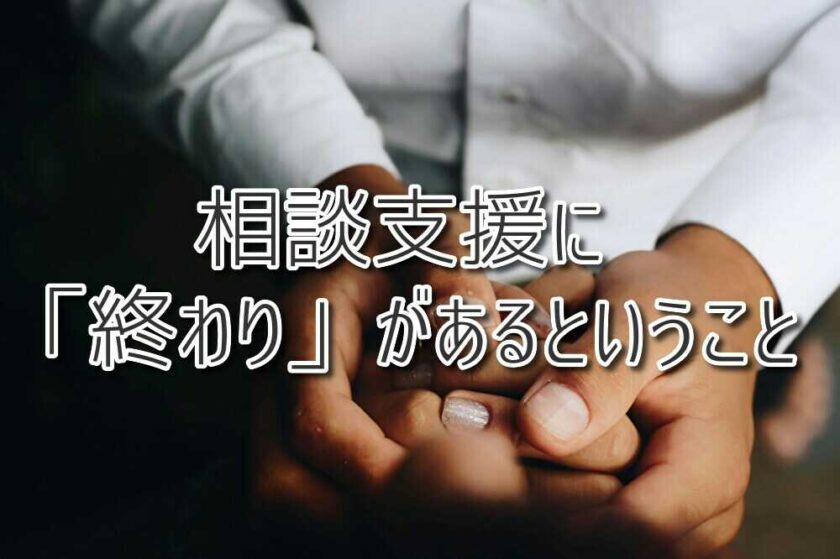ちょっと前に、連携している相談支援員さんとのお話の中で…
「支援には終わりがあるべき」って話していたことがあったんです。
お話の中で内情を聞いていると、1人の相談員さんに70~80名ほど担当している方もいるとか…
次々と新しい利用者さんが増えていって、まるで雪だるま式に膨らんでいるようでした。
このお話を聞いて考えることがありました。
「支援の終わり」って、一体なんなんでしょうか?
相談支援の仕事って、日々いろんな方のお話を聞いて、悩みに寄り添いながら、必要なサポートや制度につなげていくことを中心に、面談や連絡調整をするんですよね(きっと)
ただ、相談案件が増え続ける中で、面談の数を減らすわけにもいかず、結果的に対応する利用者数がどんどん増えてしまう…
「これ、続けていくのはさすがに無理があるな」って、思ったとしても不思議じゃないですよね。
だからきっと、その相談員さんの言葉「支援には終わりがあるべき」を再解釈すると「支援には出口をつくる」という考え方だったんだと思います。
支援を終えるって聞くと、冷たく感じるかもしれませんが…
実際には、その方がどこか別の支援機関や事業所としっかりつながっていて、そこで安定して過ごせているなら、あえて相談支援事業所がずっと関わり続ける必要って、もしかすると必要ない場合もあるかもしれないですよね。
もちろん、ケースによっては複雑で、支援の調整に時間がかかったり、長期的なフォローが必要な場合もあります。
でも、例えば通所先や入所先、就労先が見つかって落ち着いていたり、信頼できる支援者が身近にいたりすれば、いったんは相談員としての役目は終えても大丈夫だったりするかもしれません。
それで、また何かあったらいつでも戻ってきてもらえればいいですしね。
そんなふうに考えると「必要なときに必要なだけ関わる」っていうスタンスからの「支援には終わりがあるべき」という言葉だったのかもしれませんね。
この考え方って、裏を返せば、「今、本当に支援が必要な人」に、ちゃんとリソースを届けたいっていう思いから来てるんですよね。
目の前の相談をどんどん受け入れていくと、気がついたら手が回らなくなっていた…なんてことも考えられますし、支援が形だけになってしまって、実際には状況が変わっていない利用者さんも少なくないように思います。
日々の面談に追われて記録がたまっていき、書類が出せずに締切に追われる…疲れ切って、夜遅くまで事務所に残っていたなんて話も聞いたことがあります。
私たちも含めて、できることって、やっぱり限られてると思うんです…身体も時間も、無限じゃないですからね。
だからこそ、「ここまでは私たちが支援して、あとは他の人たちにバトンを渡す」っていう判断も、すごく大事だと思いました!
それは、その人を見放すってことじゃなくて、全体の福祉資源をちゃんと回すための、思いやりある選択でもあるんですよね。
これから先、ASTEPも相談支援事業所の立ち上げも視野に入れている中で、「この方に、今後もずっと同じ支援が本当に必要なのか?」って、時には立ち止まって考える必要が出てくる時があると思います。
「何でも相談支援に頼る」のではなく、自分たちでできることはしっかりやる姿勢が求められてるんじゃないかなと。
限られた社会資源を、どうやって有効に使うか?
そして、必要な人にどう届けるか?
それって、数や量だけじゃなく、支援の質とも関わってくる部分ですよね。
「支援の終わり方」って、実はその人にとっての「次のステップ」かもしれません。
支援する側としても、「終えることも支援のひとつ」っていう視点を、持ってみてもいいかもしれませんね。
これを読んでくださった相談支援員の方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです◎
お問い合わせはこちら