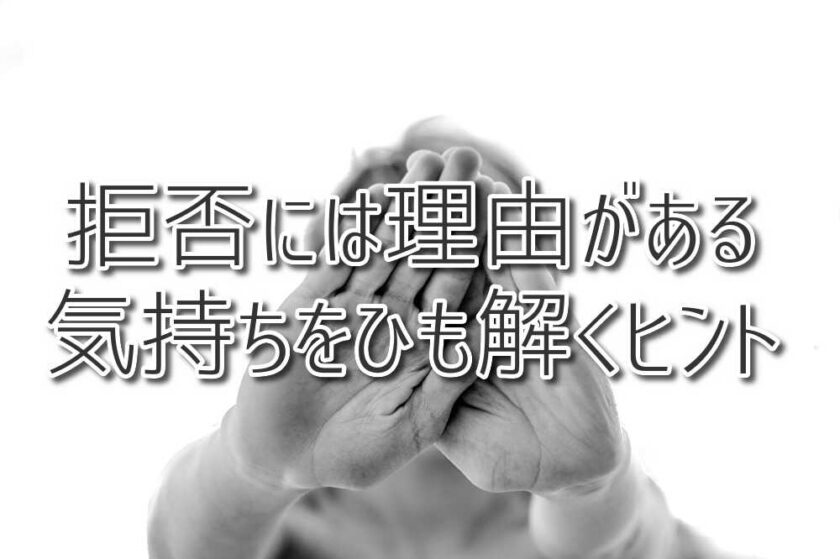活動を断固拒否
その時に「あ〜⚫︎⚫︎は嫌いなんだな」と考えるだけじゃあ思考が甘いんだよね
例えば、提示した内容をその子に合わせた仕様にチェンジしたら表情が変わったり
つまり、全て嫌だからNO!と言っているわけではなくて、少し困ったこと嫌なことがあるからNO!になることが多い肌感
↓
— ASTEP@放デイのぼやき (@ASTEP1290957) January 31, 2025
障害のある子の中には、支援者が提示した作業やスケジュールに対して「いやだ!」「できない!」と拒否することがあります。
支援者側から見ると「できないとは思えないのにな」と感じるようなことでも、本人はかたくなに「できない」と言い張ることもあります。
でも、よくよく話を聞いてみると「ちょっと難しそうだな…」「あの人がいるから嫌だな…」といった理由があることが多いんです。
ただ、それをうまく説明するのが難しくて、シンプルに「できない」と表現してしまうことがあるんですね。
じっくり時間をかけて聞いてみると、少しずつ理由を話してくれることもあります。
そして、「できない」「やらない」と言っていたことでも、本人に合うように少し内容を変えてみると、表情が柔らかくなって受け入れてくれることがあるんです。
つまり、「全部が嫌!」というわけではなく、ほんのちょっと嫌な部分があって、それが自分では乗り越えられないと感じたときに「支援を求める」より先に「やめておこう」と思ってしまうことがあるんです。
その結果、全部を拒否してしまう。でも、それを細かく言葉にするのは難しいから「できない」とだけ伝える、そんな状況なのかもしれません。
障害のある子にとって「これは嫌だけど、ここを変えたらできる」という折衷案を考えるのは、なかなか難しいことが多いですよね。
本人の中では「どこが引っかかっているのか」わかっている場合もありますが、それを言葉で伝えるのは簡単ではないし、だからこそ、支援者側が「何が気になっているのかな?」と探っていくことが大切な思考ポイントなんです。
例えば、一つひとつ細かく聞いてみると「ここはできる」「ここが苦手」「これは嫌い」と話してくれることもあります。
また、過去の経験をもとに「この部分を変えてみようか?」と提案すると、すんなり受け入れてくれることもあります。
本人にとってはほんの小さな違いが、とても大きな壁になっていることもあるので、その壁をどう乗り越えられるか、一緒に考えることが大切なんですよね。
例えば「毎日ASTEPに来るなんて嫌!やめる!」と言うけれど、「毎日じゃなければ通える」とは、なかなか言わないですよね。
「騒音がうるさいから活動が嫌!」と言うけれど「仕事が嫌なのではなく、音が嫌」とはなかなか言えないですよね。
つまり、まだまだ伝えることが未熟な子どもたちは、理由がうまく伝えられずに、結果として「やめる」「嫌だ」となってしまうことがあるんです。
だからこそ、支援者側が「この子は何に困っているんだろう?」と、もっと細かく考えてみることが大切なんです。
何が嫌なのか、何が負担になっているのかを探っていくことで、ちょっと工夫すれば受け入れられることが増えてくるはずです。方法を変えたり、環境を整えたり、支援の仕方を工夫することで、「できる」に変わることもあります。
「拒否したから、やりませんでした」では、本人が「やりたい」「できる」と出会うチャンスを失ってしまうかもしれませんし、機会損失以外なにものでもないと思ってます。
言葉のその裏には、何かしらのニーズが隠れています。
「嫌」「できない」「苦手」いわゆる気持ち。これらの気持ちを言葉や行動で示してきてくれたことをまずは認めたいですね。
そして、その気持ちの表出があったらコミュニケーションの始まり。丁寧に声を拾っていきながらアセスメント開始です!
その声にじっくり耳を傾けて、一緒に乗り越えられる方法を探っていきたいですね◎
お問い合わせはこちら